建設業務の自動化やデジタル人材の育成などを支援する業界団体
- 一般社団法人建設テック協会
- 代表理事
- 中島 貴春(株式会社フォトラクション代表取締役 CEO)
建設業界は他の産業界と同じように人材不足という問題を抱えているが、AIやICTなどの最新のテクノロジーの活用に関しては、他産業と比較して遅れているという課題がある。そうした課題に向き合い、新しいテクノロジーの調査や環境整備などを通じて、国内外の建設産業を持続的に発展させるためのエコシステムを構築しようとしているのが、建設テック協会だ。建設DXを支援するフォトラクションのCEOとして、建設テック協会の代表理事も務める中島 貴春(なかじま たかはる)氏に、建設テック協会の取り組みや役割について伺った。

(写真1)建設テック協会代表理事 中島 貴春氏
人手不足で建設物の品質管理にも課題が
──建設業界の現状や課題について教えてください。
中島氏:建設業界の一番の課題はやはり人手不足です。働き手が減っていく中でどのようにして生産性を上げていけばよいのか、どのように技術を継承していくのかといったことについて考えなければいけません。これは他産業でも同じことであると思いますが、人手不足という課題の解決に、ITやAIなどのテクノロジーを活用してどのように建設の生産性を上げていくのかが喫緊の課題になっています。私は前職でゼネコンに勤務していたのですが、そこでは施工管理も含めて、現場になかなか人が集まりませんでした。それから10年くらい経った現在ではさらに人が減り、職人のみならず管理側も人材が不足するなど、建設に関わるすべての現場で人材不足が問題になっていると感じています。
それによって、近年は建設物の品質問題などが少しずつ露呈してきました。きちんと検査すべき所を検査することができず、時間がない中で工事が進んでいき、どうしても技術知識や経験が少ない若手が検査をやらざるを得ない状況になっていることも、品質に影響しているように思います。
──最近は自動車業界で品質管理に関する問題が露呈しましたが、建設業界でも歩道橋で設計ミスによる強度不足などが明らかになったニュースもありました。
中島氏:やはり余裕がないと、実際に検査して問題があったとしても、それで手戻りが生じて工期に間に合わないことや当初の計画よりもコストがかかってしまうのではないかというプレッシャーもあるのだと思います。工期やコストからのプレッシャーから、基準を満たさない品質の状況を見なかったことにするということも起こり得ます。
これまでは、人海戦術でどうにかしていたということもありますし、昔は無茶な働き方も許容されていたため、最終的にはなんとかなってきたのでしょう。一方で海外の建設産業は、そういうことが起きないような仕組みを構築することがうまいと思っています。特にアメリカでは、建設物自体のスペックをやたらと上げ過ぎないようにしています。それに対して、日本の建設の品質は世界的に見てもトップレベルなのですが、海外の視点から見ると少しオーバースペックだったりします。
やはり、建設業界の人材不足を補うにも、しっかりした要件定義を作り上げて標準化するなど、人に依存しない仕組みを作っていく必要があると思っています。
建設テックに取り組むプレーヤーを増やしたい
──そういった、建設業の要件定義や標準化に関わる課題を、ITやAIなどの最新テクノロジーを活用して解決することを目指すのが、建設テック協会の役割なのですね。
中島氏:そもそも建設テックという言葉は、テクノロジーを活用してどう建設工事を効率よく進めるか、どうプロジェクト運営を無駄なく行うかなど、さまざまな意味合いが込められた造語です。そして、建設テック協会は2022年に建設会社や大学、ITスタートアップなどのみなさんと一緒に、建設テックについて語り合う場を作りたいということから設立した業界団体です。
もともとは2018年くらいにソフトバンクや大学などから、AIを活用した建設業界向けの研究会が作れないかという相談が、フォトラクションに持ちかけられたことから始まりました。その頃は論文執筆など、学生に対する活動が中心だったのですが、そのうちにAIと建設を組み合わせた論文が次々と生まれてきました。そこで、2021年頃に、もう少し民間企業の活動も取り入れながら、きちんと体系立ててやっていきたいという話になり、2022年に一般社団法人化して展開しています。
とはいえ、建設業界の課題を、最新のテクノロジーだけで全て解決できるとは思っていません。まずは、とにかく建設テックに取り組むプレーヤーを増やさなければ、なかなか前に進んでいかない状況があります。アメリカの建設業界を見ていると、やはり日本と比べて建設テックに積極的に取り組む方々が多く、ITへの投資が進んでいることにより市場も大きくなっているのです。もちろん、プレーヤーが増えれば淘汰されたり、統合されたりしてしまいますし、そもそも全く使えない技術もたくさん出てくると思います。
ただ、建設テックに取り組むプレーヤーが増えることで全体的なレベルや質が上がっていくと思うため、プレーヤーを増やすという面でも建設テック協会の役割は大きいと思っています。
──建設テックに関しても、やはり日本よりアメリカの方が進んでいるのですね。
中島氏:そうですね。でも日本は昔から、建設業界全体の環境整備にしっかりと取り組んできました。特に建設業の場合は業界の基準がきちんと定められており、国や行政との仕事が多いため、環境整備については、全然アメリカにも負けていないと思います。
また、建設技術などに関しても、高度経済成長期を経験したことで非常に成熟していますし、レベルの高い分野であると思っています。ただ、建設テックの取り組みに関していうと、やはりアメリカの方が積極的にやっている現状があるため、建設テック協会としてもまずは建設テックの取り組みを促進するために、業界の皆で集まってやれることをやっていくっていうのが現状ですね。

(図1)建設テックの普及を目的として企業や大学が参加する建設テック協会
建設テック協会の主な役割はコミュニティ作り
──具体的に建設テックによって、課題を解決している事例があれば教えてください。
中島氏:例えば、現場での写真管理や図面管理は、扱うデータが膨大なのです。建設物の写真だけでも何十万枚も撮ったりしますし、それを記録に残していくためにいろいろな情報を付加したり、図面と紐付けたりします。従来の現場ではデジカメを持っていって写真を撮り、その写真をカメラにつながれたパソコンに転送して種別ごとにフォルダで管理するなどの手作業が発生していました。
そういった作業は非常に手間がかかるため、フォトラクションでは施工管理を効率化するサービスとして、最新技術を活用したアプリケーションを提供しています。現場での撮影から管理までの機能を全てスマートフォンで行い、写真を撮るだけでAIが画像を解析して自動的に情報が付加されてフォルダに整理され、簡単な操作ですぐに必要な写真が見ることができるなど、現場での業務を効率化します。
他にも、スマートフォンを3Dスキャナーとして利用し、建物を建てる時に使う鉄筋の柱などを撮影して点群データを作り、図面と照合しながら検査するといった取り組みをしている企業もいます。特に最近は、AIを活用したBPO(Business Process Outsourcing:企業業務の外部委託)に力を入れる企業も出てきました。単にアプリケーションを使うだけではどうしても解決できない課題、例えば建物のどこで何を検査するのかといったことも、AI-BPOを使えば経験が浅い若手の方でも図面から理解することができます。
──建設業界における生成AIの活用としては、どんなことが想定されるでしょうか。
中島氏:いろいろなことができると思っています。現状でも、例えばフォトラクションで作っていた図面をチャットGPTに投げてみると、意外ときちんと読み込めたりします。ですので、書類作成の自動化などの業務には生成AIは非常に向いていると思います。
特に、AI-BPOとは非常に相性が良く、生成AIをそのまま組み込んでユーザーに使ってもらうのは難しいと思いますが、オペレータが生成AIを活用してユーザーが望む結果を返すというようなことができれば広がっていきそうです。
──建設テック協会は、そうした企業の取り組みを後押ししているのですね。
中島氏:実は建設テック協会の活動としては、積極的に成果物を求めているわけではないのです。参加企業には建設会社もいればIT企業、大学もいるので、成果を求めようとするとどうしても利害関係が生まれてしまいます。ですので、協会の趣旨としてはコミュニティを作っていくことを目的にし、戦略的にこういうことやっていきましょうとか、こういう成果物を出しましょうということはあえてやっていません。
そのため、協会の具体的な取り組みとしては、みんなで集まって複数の会社から近況を発表していただいたり、その後の懇親会で情報交換したりといった感じなのです。
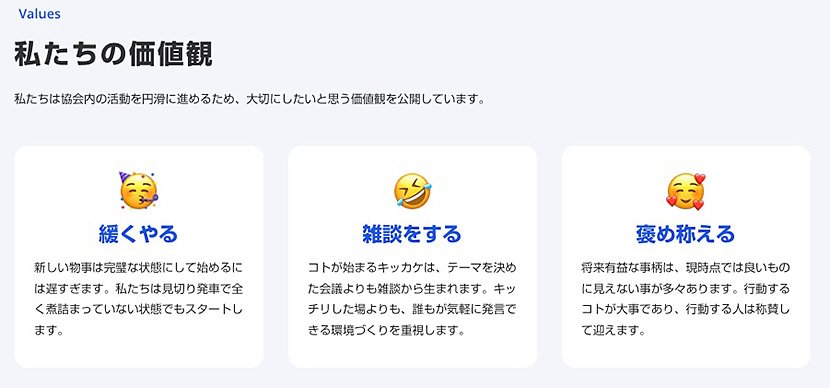
(図2)建設テック協会の役割の1つはコミュニティの創生
建設テックに興味を持つ学生の人材育成も
──建設関係の学生さんだと、やはりITとかAIに関してはそれほど知識がないと思うのですが、そういった学生さんの建設テック向け人材育成なども協会の役割になっているのでしょうか。
中島氏:建設業自体に人が流れてこなくなっているため、そこはやはり業界全体でうまくPRして学生さんたちに興味を持っていただきたいと思っています。今期は、建設業界の中でテクノロジーを活用している企業の方に来ていただき、学生さん達に話をしてもらう機会を作りました。建設関係の学生さんは、どうしても将来の選択肢が設計か施工しかないと思っているようですが、大手ゼネコンなどでは建設分野とは全く異なる研究をしていたりもするため、まずはそのような実態を知ってもらうところから始めてみようと思っています。やはり、第一線で働く方と関わる機会は大学だけではなかなか作ることができないと思うため、そこは協会として支援していきます。
逆に、ITやAIに興味があっても、建設業界の中でどう生かせばよいのか分からない、自分の将来とどうつながるのかよく分からないと思っている学生さんも多いでしょう。そういった学生さんにも、建設テックのことを知ってもらうきっかけになればと思っています。
──実際に、IT業界の方から建設業界に来る人も多いのですか。
中島氏:最近は多いですね。IT業界から大手ゼネコンに来ましたとか、後はゼネコンでもいろいろと役割が変容してきていて、スタートアップと協業するチームやIT投資をするチームが発足するなど、各社が新しい取り組みを始めています。

(図3)学生から法人まで幅広く集まっている建設テック協会の会員
業務の標準化が地場ゼネコンの競争力向上に
──建設テック協会や、建設テック全体に関する今後の展望について教えてください。
中島氏:協会としては、今後もコミュニティを大事にしていきたいと思っています。建設テック全体としては、やはり母数が大きくなっていかなければだめだと思っていて、そもそも建設業は日本のGDPの1割強を占めるくらい巨大な産業なのです。それを支援する建設テックも、本来であればそれなりの市場規模があるはずです。そのような市場をみんなで作っていきたいと思っています。
特に最近は、積極的にデジタル化に取り組む建設会社が多いと思っています。建設テックでも最近スタートアップが増えてきた理由として、2012年頃から建設業界の中でiPadが広まってきたということがあります。パソコンは現場に持っていけないため、現場では一気にiPadが普及したのですが、今でも他の産業と比較すると、モバイルクラウドが普及していると思います。大手ゼネコンでは、全くモバイルクラウドを導入していない企業はほぼないため、そうなると現場で使うソフトウェアやアプリが重要になってきます。
また、モバイルへの投資も非常に安価になりました。昔でしたらサーバ1台立てるために何千万円もかかっていたのが、クラウドを利用することにより数万円でモバイル環境を整えることができます。そのため、まずは建設テックを使ってみることが大事だと考えています。実際に現場で使えるかどうかは、後で決めればよいのです。そういう考えを持つ方を、増やしていきたいと思っています。
──人材不足の課題にしても、大手ゼネコンには中堅や地場のゼネコンからどんどん人が流れていき、地方の地場ゼネコンが大変苦労しています。今後は、大都市と地方のゼネコンの人材確保を平準化するような役割も、建設テック協会が担っていくと考えてよいのでしょうか。
中島氏:そうですね、そういう手伝いができるとよいと思っています。建設テックによって仕事が平準化や標準化されたりすると、大手とそれ以外のゼネコンで業務の内容に差が付くこともなくなっていくでしょう。
また、最近は地場ゼネコンが、独自の魅力作りを始めていたりします。例えば、首都圏よりも給与水準を高くするとか、アニメを使って企業PRをしたり街づくりに力を入れたりなど、各社でいろいろと特色を打ち出し始めています。そういったことが競争の源泉になるようにするためにも、建設テックで業務を標準化して、できるだけ少ない人数でもよい物が作れるようになればよいと思います。
ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など
ございましたらお気軽にお問い合わせください。
最新の特集

水素実装元年
















