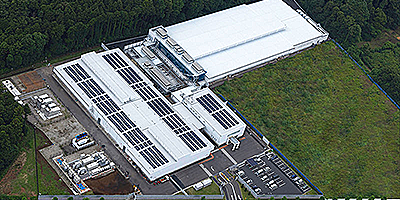データセンターの現状と課題を徹底解説!最新の冷却技術や方法も紹介
目次
- ▼1. データセンターの特徴とは
- ・データセンターの種類
- ▼2. データセンター業界の現状
- ・日本のデータセンターサービス市場は増加傾向にある
- ・日本のデータセンターは関東に集中している
- ▼3. データセンターの課題
- ・①冷却用設備の稼働による電力消費量の増加
- ・②環境負荷が大きい
- ・③データセンターを運用する人材不足
- ▼4. データセンターに冷却設備が重要な理由
- ▼5. データセンターのエネルギー効率を高める主な冷却方法
- ・水冷リアドア方式
- ・コールドプレート冷却方式
- ・液浸冷却方式
- ▼6. AIの大規模データに対応したコンテナ型データセンター
- ・事例|株式会社ミライト・ワン池袋技術センターに「M:MDC(モルゲンロットモバイルデータセンター)」を設置
- ▼7. まとめ
近年、AI技術の進展やデジタルトランスフォーメーション(DX)の加速により、企業が扱うデータ量は急速に増加している。これに伴い、大量のデータを安全に保管・処理するための施設であるデータセンターの重要性が高まっている。
本記事では、データセンターの基本的な特徴や種類から、現在の市場動向、課題、最新の冷却技術までを解説する。ぜひ参考にしてみてほしい。
データセンターの特徴とは

データセンターとは、サーバーやネットワーク機器を設置し、企業が保有するデータを大量に保存して運用するための専用施設のこと。データセンター内部には、サーバーやルーターなどを収納するラック(専用棚)が並び、ネットワーク機器や冷却装置、大容量電源などの設備が整備されている。
さらに、地震によるサーバーの破損を防止するため、データセンターには地震の揺れを吸収する耐震・免震構造がとられている。万が一、災害などの影響で停電が起こっても、非常用の電源設備が備わっている施設も見られる。
データセンターは機密情報を保管するため、強固なセキュリティが実装されている。
データセンターの種類
データセンターには、自社サーバーをデータセンター内に設置する「ハウジング」と、ベンダーのサーバーを借りる「ホスティング」の主に2種類がある。
それぞれの概要、メリット・デメリットは以下のとおり。
| 名称 | ハウジング | ホスティング |
| 概要 | ベンダーが提供するデータセンターのスペースを借りて、自社サーバーを設置すること | ベンダーがデータセンター内で運用するサーバーを遠隔から利用すること |
| メリット | ・機密情報を安全に運用できることで、BCP対策につながる ・運用保守サポートが利用できる ・カスタマイズしやすい ・自社サーバールームよりも低コストで運用できる |
・導入がスムーズ ・ハウジングよりも保守管理の手間がかからない ・セキュリティ対策が実施されている ・ハウジングよりもコストをかけず利用できる |
| デメリット | ・自社サーバーを用意する必要があるので、ノウハウの持つ人材を社内で確保しなければならない ・障害対応や保守管理を自社でカバーしなければならない ・ホスティングと比較して、コストがかかる傾向にある |
・利用できるサーバー構成の自由度が低い ・障害発生時の対応は任せられるが、自社でできることはなく、復旧を待つのみとなる |
| 主な利用目的 | 中小企業や大企業がBCP対策やコスト削減を目的に利用 | 個人ユーザーや中小企業など幅広い利用者が運用コストを抑える目的で利用 |
データセンター業界の現状
続いて、データセンター業界の現状を見ていこう。
近年、ChatGPTの登場を皮切りに、生成AIサービスの利用が世界で広まると同時に、データセンター需要も高まっている。生成AIサービスの利用にサーバーの運用は欠かすことができず、大手テック企業を中心に、データセンターへの大規模な投資が加速している状況がある。
今後、企業や自治体などでの生成AIサービスの導入も本格的に進むと考えられ、データセンター需要はますます増加するだろう。
ここでは、国内市場に目を向け、データセンターの市場規模や設置状況について紹介する。
日本のデータセンターサービス市場は増加傾向にある
総務省の「令和6年版 情報通信白書」では、2022年における日本のデータセンターサービスの市場規模(売上高)は、2兆938億円と報告された。2027年にはさらに成長し、4兆1,862億円に達すると見込まれている。
データセンターサービスの国内市場は拡大傾向で、生成AIサービスの普及によって今後も需要が増加すると予測される。
参考:令和6年版 情報通信白書 図表Ⅱ-1-8-2 日本のデータセンターサービス市場規模(売上高)の推移及び予測|総務省
関連リンク
拡大するデータセンター市場
日本のデータセンターは関東に集中している
日本のデータセンターの立地状況を見ると、約6割が関東に、約2割が関西に集中している。データセンターへの交通アクセスが良いことから、データセンターは都市部に集中する傾向が見られる。
データセンターが物理的に遠い場所に設置されている場合、データ移動の遅延や待ち時間を示すレイテンシーが発生する可能性もあるため、利用者の近くに設置する方が望ましいだろう。
地方には、都市部にある企業のバックアップ用や、地元企業向けの小型データセンターが設置されることが少なくない。また、地震大国である日本では、地震や洪水などの災害リスクが少ない場所が、データセンターの建設地として選定されるケースも見られる。
データセンターの課題
近年、需要が高まるデータセンターだが、いくつかの課題がある。ここでは、次の3つの課題を紹介する。
①冷却用設備の稼働による電力消費量の増加
②環境負荷が大きい
③データセンターを運用する人材不足
①冷却用設備の稼働による電力消費量の増加
データセンターでは、膨大な量のデータを処理するため、サーバーが発熱する。サーバー自体の電力消費量が問題となっているが、サーバーの熱を排熱するための冷却用設備の消費電力量の増加も課題となっている。
環境省の資料では、データセンターの消費電力の約45%が冷却設備によるものと記載されており、サーバー自体の電力消費とあわせて大きな負担を抱えている。
電力消費コストがかかることはもちろん、次で説明するように、環境負荷の観点からも重要な問題といえるだろう。
②環境負荷が大きい
サーバーや冷却用設備などで構成されるデータセンターの電気消費量が増えることで、環境負荷が大きくなる点も懸念されている。これは、エネルギーの大量消費によって、CO2をはじめとする温室効果ガスが大量に排出されると考えられるためである。
生成AIサービスの爆発的な普及によって、アメリカのデータセンターから排出されたCO2は2018年以降3倍に増加したという研究報告もある。
2050年のカーボンニュートラル実現へ向けて取り組みが世界中で進められるなか、データセンターの消費電力量やCO2排出量を低減するための新技術が求められている。
参考:AIブームで特需、米国内のデータセンター CO2排出量が3倍に|MIT Technology Review
③データセンターを運用する人材不足
データセンターやサーバーを運用する人材が不足している点も、課題として挙げられる。
デジタル技術の進化に伴い、生成されるデータ量は急増している。さらに、多様なシステムやアプリケーションの登場により、データセンターの構造は複雑化している。とくに、地方にあるデータセンターでは、複雑な運用や障害対応が行えるエンジニアの確保が難しく、人手不足が深刻化している状況も見られる。
そこで、信頼できる外部パートナーへの依頼や、データセンター運用管理業務の自動化・省人化が必要とされている。
データセンターに冷却設備が重要な理由

データセンターは、サーバーやルーターなどさまざまな要素で構成されている。ここでは、データセンターにおいて45%の電気消費量を占めるとされている「冷却設備」に着目していこう。
データセンターで使われている機器は電力によって動作しており、その過程で大量の熱エネルギーが生成される。膨大なデータ量処理を継続的に行うサーバーは著しく温度が上昇し、適切な温度管理ができなければシャットダウンや故障を引き起こす可能性がある。
そこで必要となるのが、冷却設備である。風や水などを使った冷却技術によって熱を分散させ、大気へ放出させることなどによって、サーバーなど機器の過熱を防ぐことで、トラブルを回避する。
過熱によりサーバーが停止してしまうと、ビジネスに大きな支障をもたらすと考えられるため、データセンターでは効果的な冷却設備の稼働が欠かせない。また、近年では環境への配慮も重視されていることから、環境にやさしくエネルギー効率に優れた冷却設備が求められている。
データセンターのエネルギー効率を高める主な冷却方法
最近のAI生成サービスをはじめとしたデジタル技術の進展によって、データセンターの稼働も増加している。従来の空調による冷却方式のみでは排熱効率が悪く、十分な対応が困難になっている状況が見られる。
現在、サーバーなどのICT機器を冷却する方法として主流なものは、空冷式と水冷式だ。空冷式は、冷却ファンによって空気の力でCPUやGPUを冷却する。水冷式は冷却水を循環させることで直接的に熱源にアプローチする。主にGPUベンダーが提供することが多い。
それ以外に、新たな冷却方法として、次の3つの技術に注目が集まっている。
● 水冷リアドア方式
● コールドプレート冷却方式
● 液浸冷却方式
ここでは、それぞれの方法について詳しく見ていこう。
水冷リアドア方式
水冷リアドア方式は、データセンターの冷却方法の一つとして注目されている技術である。この方法の特徴は、サーバーラックの背面(リア)に冷水を通した熱交換器とファンを設置し、サーバーから排出される高温の排気を冷却する点にある。
サーバーからの熱を排出直後に回収するため、熱交換効率が高まることで、優れた冷却性能とエネルギー効率を実現する、サーバーラック単位の冷却方式である。
とくに最近では、AIの発展に伴い高性能なGPUサーバーから発生する大量の熱に対応するため、より効果的な水冷式の空調機が、株式会社NTTファシリティーズなどによって開発されている。
参考:水冷式空調機/CyberAir® リアドア型|NTTファシリティーズ
コールドプレート冷却方式
コールドプレート冷却方式は、ICT機器の発熱部に冷却板(コールドプレート)を取り付けて、チップなどの発熱を取り除く技術である。
コールドプレートを介して冷却液が発熱部からの熱を直接吸収し、冷却を行う仕組みとなっている。
液浸冷却方式
液浸冷却方式は、絶縁性を持つ特殊な冷却液が入った液槽にサーバーを丸ごと浸して冷却を行う技術である。
サーバー全体に冷却液が直接触れて熱を吸収するため、従来の冷却ファンが不要となり、高い冷却性能とエネルギー効率を実現している。
AIの大規模データに対応したコンテナ型データセンター
急速に発展するAI技術に対応するため、高性能なGPUサーバーを効率的に設置・運用できるコンテナ型データセンターが注目を集めている。

株式会社ミライト・ワンによる「コンテナ型データセンター」は、高排熱処理空調を搭載し、建築物として扱われないため、従来のデータセンターと比べて大幅に導入時期を短縮できる点が特長である。
用途に応じた柔軟な設計が可能で、高い拡張性を備えている。また、高排熱・省エネ空調が完備されているため、AIを使った膨大な計算量にも対応可能である。
さらに、太陽光発電や風力発電など、再生可能エネルギー設備とも連携できるので、出力抑制による電力損失を防ぎつつ、都市型データセンターが抱える電力不足などの課題にも対応できる。
その他、計算力の効率的な活用を実現するため、計算力を必要とする企業と保有する企業をマッチングするサービス「Cloud Bouquet™(クラウドブーケ)」も提供。これにより、よりフレキシブルなコンテナ型データセンターの活用が可能となる。詳しくは、以下のサイトを参考にしてほしい。
事例|株式会社ミライト・ワン池袋技術センターに「M:MDC(モルゲンロットモバイルデータセンター)」を設置
株式会社ミライト・ワン、モルゲンロット株式会社、WOODMAN株式会社の3社は、GPUベースの産業用コンテナ型データセンターソリューション「M:MDC(モルゲンロットモバイルデータセンター)」を共同開発し、ミライト・ワン池袋技術センターに設置。2022年12月1日よりサービス提供を開始した。
近年、コンピューターグラフィクス(CG)レンダリングは、写実的なCG制作や自動車開発、都市開発、研究機関など、さまざまな分野で利用されており、テラバイト単位の大容量データの演算処理が必要とされている。しかし、高速演算用ハードウェアの高額な導入コストや、大容量データ転送時のオペレーションコストが課題となっていた。
「M:MDC」は、利用者の近くに設置することでデータ転送コストを抑制し、クラウドでの計算力提供により初期投資を不要とする。これにより、大規模データセンターやスーパーコンピューターと比べて、はるかに低コストで高速演算能力を提供することが可能となる。
開発された第一号コンテナでは、計算力の提供だけでなく、各種技術検証や見学受け入れも実施している。

関連リンク
GPUベースの産業用コンテナ型データセンターソリューション 「M:MDC(モルゲンロットモバイルデータセンター)」 のサービス開始
まとめ
本記事では、データセンターの基本的な特徴から、現状の課題、最新の冷却技術まで解説した。
生成AIサービスの登場により、データセンター需要は急速に拡大している。同時に、サーバーの発熱処理や消費電力の効率化が新たな課題として認識されるようになった。そこで、水冷方式やコールドプレート冷却方式、液浸冷却方式など、新しい冷却技術が開発されている。
株式会社ミライト・ワンが提供する「コンテナ型データセンター」は、高排熱処理空調を搭載し、再生可能エネルギー設備との連携も可能なソリューションとして注目を集めている。
今後も拡大が予想されるデータセンター市場において、環境負荷の低減と高い処理能力の両立が求められている。柔軟な拡張性と効率的な冷却システムを備えたコンテナ型データセンターは、これらの課題を解決する有効な選択肢となるだろう。詳しくは、以下のサイトを参考にしてほしい。
ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など
ございましたらお気軽にお問い合わせください。
最新の特集

水素実装元年