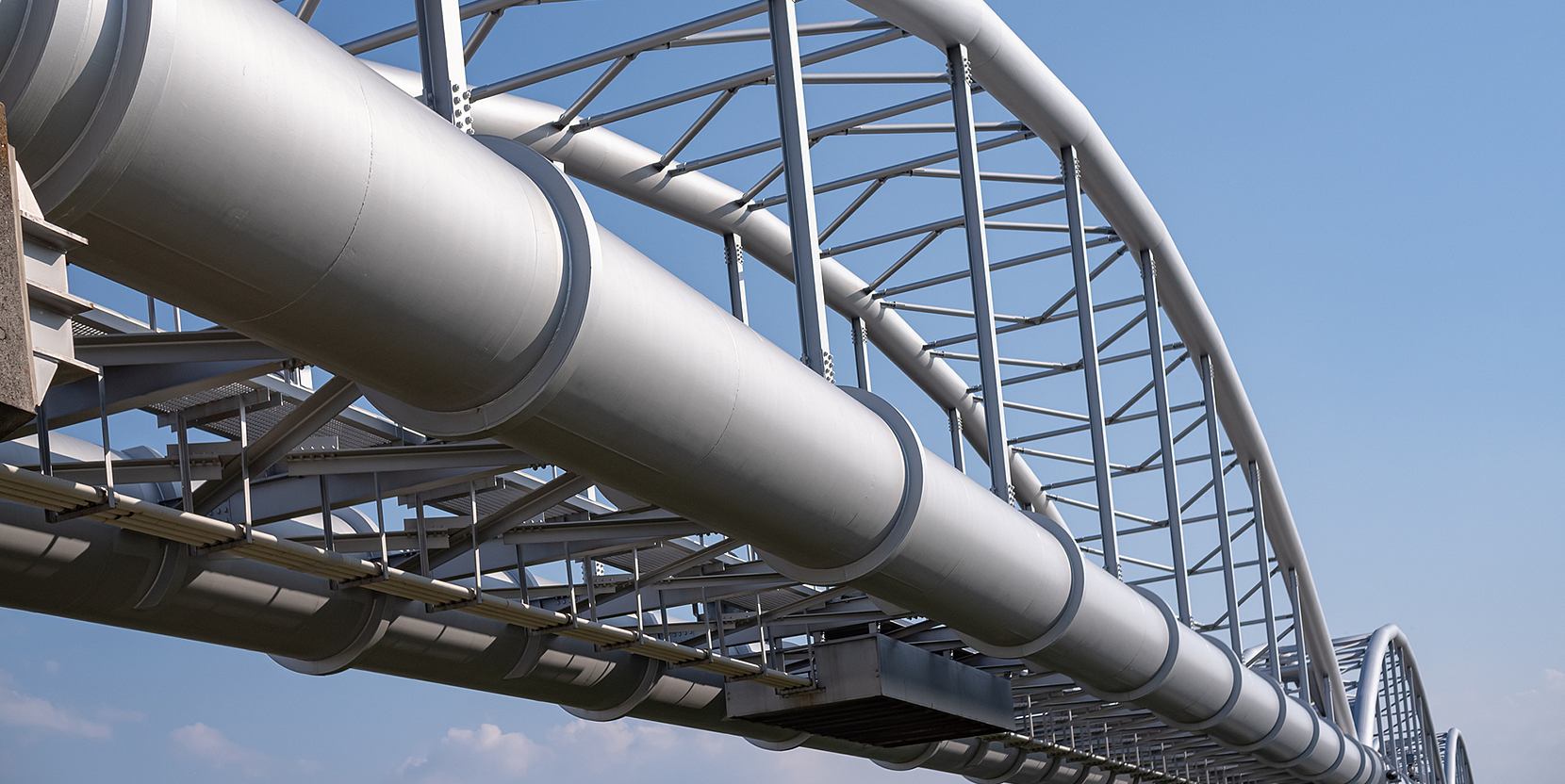水道インフラの重要性と課題、具体的な対策とは
日本の水道インフラは、生活や産業活動を支える社会の基盤である。しかし現在、その水道インフラは老朽化や人手不足など、さまざまな課題に直面している。
本記事では、水道インフラの重要性をあらためて確認するとともに、現在の主な課題と対策について解説する。
水道インフラは人々の生活を支える重要な生命線

水道インフラは、家庭や学校、企業、工場、医療機関など、社会のあらゆる場所で水を安定供給する基盤であり、人々の健康的な生活や経済活動を支える不可欠な存在である。
2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」を意味するSDGs(Sustainable Development Goals)においても、「安全な水とトイレを世界中に」が6番目の目標に掲げられ、水道インフラの重要性が示されている。
日本の水道普及率は98.2%に達しており、世界でも数少ない水道水をそのまま飲める国の一つとなっている。そのような国は世界でわずか11カ国しか存在せず、日本の水道インフラは極めて高い水準にあるといえるだろう。
蛇口をひねれば安全な水を飲める状況ではあるが、災害や事故が原因で水道インフラが機能しなくなれば、人々の生活や経済活動に大きな影響が出る可能性がある。近年、国内では震災時の断水や水道管の老朽化による道路陥没などが発生していることから、水道インフラの重要性が改めて問われている。
水道インフラに関する4つの課題
ここでは、日本の水道インフラに関する4つの課題について解説する。
①水道管の老朽化が進んでいる
②職員数の減少や高齢化が深刻化している
③一部の小規模水道事業者が経営難に陥っている
④上下水道事業からのCO2排出量が多い
①水道管の老朽化が進んでいる

全国の水道管は1960〜70年代の高度経済成長期に敷設されたものが多く、現在では老朽化と耐震性の低さが課題となっている。
公益社団法人日本水道協会によると、2022年時点で、すべての水道管において耐震適合している割合は37.1%だった。6割以上が地震に弱い水道管のままであり、地震による破裂により断水するリスクが高まることが懸念されている。
また、全国に張り巡らされた約74万kmの水道管のうち、法定耐用年数である40年を超えた水道管の割合を示す「管路経年化率」は、2022年時点で約23.6%に達する。一方、更新作業は大きく遅れており、同年に更新された水道管の長さは約4,800kmで、更新率はわずか0.64%にとどまる。このままの更新ペースが続けば、20年後には経年化率が69%に達すると予測されており、早急な対応が求められている。
さらに、社会や経済を支えるインフラとして重要な「工業用水道管」においても、同様に老朽化が進行しているため、対策が急務である。工業用水道管は大規模な生産施設や工場群に接続されていて、破損が起こればさまざまな企業の生産活動に深刻な影響を及ぼすリスクがある。
特に、都市部では施工年代が古く埋設深度も浅いため路面への直接的な影響が大きく、配管の破損によって路面陥没や交通の混乱など、二次的被害に発展する恐れもあるだろう。
関連リンク
水道管の老朽化問題に関する現状とは?原因や対策、新技術も解説
②職員数の減少や高齢化が深刻化している
水道事業に従事する職員の減少と高齢化が深刻化しており、水道インフラのメンテナンス業務に影響を及ぼしている。
老朽化が進む水道管に対し、計画的な点検や補修を行わなければ劣化の進行が加速する恐れがある。しかし、人員不足により自治体側の体制が整っておらず、水道管のメンテナンスや更新工事の発注業務などに支障をきたしている。
公益社団法人日本水道協会の「水道統計総論(令和4年度)」によると、2022年時点で水道事業に従事する職員は72,758人で、1990年の80,105人から減少している。なかでも、特に技術者や熟練した作業員が不足しており、若手人材の育成が急務となっている。
水道管の更新工事に対する需要は高まっているものの、水道事業者の規模によっては人材の確保が難しく、対応が遅れている点が懸念されている。
③一部の小規模水道事業者が経営難に陥っている

小規模水道事業者では、経営難によって水道設備の更新や維持が難しくなっている点も課題としてあげられる。
水道事業は公益事業として捉えられ、地域の実情を踏まえて市町村が主体となって運営する体制が一般的である。財源は主に水道料金に依存しており、税金ではなく「独立採算制」が基本となっている。
しかし、人口減少や節水志向の広がりによって水の使用量は年々減少し、水道料金による収入では経営が困難になる事業者も見受けられる。特に経営規模の小さい自治体では、設備の更新や老朽化対策に必要な費用や人材を確保することが難しい状況にあると考えられる。このような事態が続けば、水道サービスを維持できない地域が増加するリスクもある。
④上下水道事業からのCO2排出量が多い
上下水道事業は、行政サービスの中でもCO2排出量が多い分野の一つである。水道管を使って各地に水を届ける方法は、車で輸送する手段と比べて環境負荷が低いとされているが、それでも上下水道の運用には大量の電力が必要とされる。
実際、上下水道事業全体で年間約150億kWhの電力を消費しており、これは日本全体の電力使用量の約1.5%に相当する。
日本は2050年にカーボンニュートラルを実現すると宣言しているため、上下水道分野でもエネルギー使用の見直しが急務となっている。太陽光発電を導入するなど、水道事業者にもCO2排出量の削減に向けた取り組みが求められている。
水道インフラをめぐる課題への対応策
続いて、水道インフラをめぐる課題への対応策について解説する。
①アセットマネジメントに取り組む
②官民連携により水道事業を運営する
③太陽光発電設備を導入する
④新技術を活用する
①アセットマネジメントに取り組む
水道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)について、厚生労働省の資料では以下のように定義されている。
| <水道事業におけるアセットマネジメントの定義> "水道ビジョンに掲げた持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動" 引用:水道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)に関する手引き|厚生労働省 |
アセットマネジメントを実施することで、中長期的な視点から資産の状態や劣化の進行度を把握し、更新時期や優先順位を的確に判断できるようになる。これにより、更新工事のための計画的な投資が可能となるだろう。
さらに、断水事故などのトラブルの予防対策や、災害発生時の影響を最小限に抑える効果も期待されている。
②官民連携により水道事業を運営する

水道インフラの効率的な運営に向けて、官民連携で水道事業を担う「ウォーターPPP」と呼ばれる方式が注目されている。これは、水道、工業用水道、下水道など水のインフラ分野において、公共と民間が連携して公共施設を管理・運営することを指す。一般的に10年の長期契約で、民間事業が維持管理と更新のマネジメントを行い、収益を共有する仕組みである。
例えば、群馬県では3市5町が水道事業の広域連携を実施。民間企業に水道事業の運営や更新工事を委託し、収益が大幅に改善した事例がある。
③太陽光発電設備を導入する
上下水道事業からのCO2排出量を削減するために、太陽光発電設備の導入も有効な選択肢とされている。
その理由として、水道施設は敷地面積が広く発電設備を設置しやすい点があげられる。また、日光を遮断する建物が少なく日陰になりにくく、安定した発電が見込める。加えて、上下水道施設は24時間稼働のため、発電した電力をムダなく活用しやすい点もメリットといえる。行政が運営している水道事業は人々の生活に欠かせないことから倒産リスクが低く、長期的にみて再生可能エネルギーの発電設備を運用しやすいだろう。
株式会社ミライト・ワンは「太陽光発電システムのエンジニアリング&サービス」を提供している。これまで培ってきた施工技術力やノウハウ、豊富な実績に基づき、企画から設計、調達、施工、保守、運用までをトータルで提案している。詳しくは、以下のリンクをチェックしてみてほしい。
関連リンク
再生可能エネルギーとは?種類やメリット・デメリット、導入方法を紹介
④新技術を活用する
業務効率化や人員不足対策、設備の長寿命化を図るために、政府より新技術の活用が推奨されている。水道インフラのメンテナンスや更新などに役立つ新技術の例は、以下のとおり。
| 種類 | 概要 |
| 水道スマートメーター遠隔監視システム | 工業用水などの流量の遠隔監視や自動検針が可能なシステム。通常の検針業務の効率化やペーパーレス化に加え、災害時に現場を訪れることなく状況を即座に把握することも可能。 |
| AIによる水道管の劣化診断 | 既存の水道管に関するデータと、独自の環境データベースやAIを活用し、水道管の劣化状態や漏水リスクを予測する技術。マップ上に可視化された情報をもとに、自動で更新計画を立案できる。 |
| 水道設備の環境改善技術 | 給排水管に巻き付けて使用するセルフクリーニング装置。配管に付着するスケールを取り除き、配管内部の清浄化・長寿命化を促進する。 |
| ドローンによる水管橋の点検 | 水管橋や配水池、建物壁面などのインフラ施設で実施するドローンによる点検サービス。可視光・赤外線カメラをドローンに搭載し、目視点検よりも正確・安全に水管橋の劣化箇所を発見する。 |
株式会社ミライト・ワンは、水道事業者の支援に向けて「水道DXソリューション」を提供している。水道スマートメーター遠隔監視システムの提供をはじめ、AIを活用した劣化診断や、環境改善装置「ナノゲート」の導入支援、ドローンによるインフラ点検など、現場のニーズに応じた多様なサービスを展開している。
AIやIoTなどのデジタル技術を活用し、上下水道施設の管理やメンテナンスの効率化を検討している方は、以下のリンクをチェックしてみてほしい。
まとめ
日本の水道インフラは、人々の暮らしや産業活動を支える基盤として、重要な役割を担っている。一方で、設備の老朽化や人員不足と高齢化、環境負荷など、多くの課題が浮き彫りになっている。
株式会社ミライト・ワンは、水道事業者に対し水道DXソリューションを提供している。具体的には、水道スマートメーターの遠隔監視や、AIを活用した設備診断、環境改善装置、ドローンによる点検支援など、老朽化対策に寄与するサービスだけでなく、太陽光発電設備の導入により環境負荷の軽減も支援している。
持続可能な水道インフラのサービス提供を目指している水道事業者の方は、以下のリンクをチェックしてみてほしい。
水道スマートメーター遠隔監視システム
水道管劣化予測・影響度評価・更新計画策定ソリューション
上下水設備の環境改善装置「ナノゲート」
上・下水道関連事業 上下水道管路・施設の老朽対策・維持更新
ドローンフライトソリューション
太陽光発電システムのエンジニアリング&サービス
ミライト・ワンのソリューションに関するご質問、ご相談など
ございましたらお気軽にお問い合わせください。
最新の特集

水素実装元年